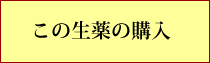ハトが好んで食べることから、はとむぎの名がつきました。中国原産といわれ、アジア各地で栽培されています。4月下旬~5月上旬に株間20~30cmに2~3粒ずつ点蒔し、9月下旬、果実が成熟する頃に刈り取って乾燥させます。
明治以前はシコクムギ(四石麦)といわれ10アール当たり4石の収量があるからといわれています。外見は、「ジュズダマ」によく似ていますが、ジュズダマが多年草なのに対してはとむぎは1年草 です。ジュズダマの花序は上向きなのに対して、はとむぎはたれる。 ジュズダマの果実はホーロウ質で硬い(指で押してもつぶれない)のに対し、 はとむぎは柔らかい(指でつぶれる)。
硬い殻をむいた仁の部分をヨクイニンと言い、単独でイボの薬として、又は肌荒れなどに用いるほか、金棒薬の材料として用いられます。
成分
種仁の成分は、でんぷん 52%、粗蛋白18%、粗脂肪7%、灰分3%
分解によるアミノ酸は、Leucine、Tyrosineに富んでいます。
ほかに、腫瘍抑制作用を有する「コイクセノライド」を含んでいます。
→はとむぎ(ハトムギ) 、ヨクイニン錠、ヨクイニンエキス、よくいにん 原形
→ ヨクイニンを使用した漢方薬 麻杏薏甘湯 、薏苡仁湯、参苓白朮散