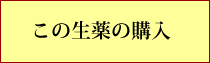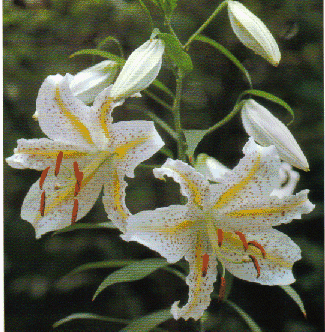東北から近畿地方にかけての山地や草地に自生し、夏に、大きく開いた漏斗状の白い花を数個横向きに開花します。花被片の中央に黄色の条線が入り、赤褐色の斑点が数多くあります。灼熱の太陽の下、強い香りを放ちながらそよ風に揺らぐ姿は、ユリの王様と称されます。
東北から近畿地方にかけての山地や草地に自生し、夏に、大きく開いた漏斗状の白い花を数個横向きに開花します。花被片の中央に黄色の条線が入り、赤褐色の斑点が数多くあります。灼熱の太陽の下、強い香りを放ちながらそよ風に揺らぐ姿は、ユリの王様と称されます。ユリは万葉集に十首が詠まれているように、古くから観賞されていましたが、多糖類のグルコマンナンを多量に含む鱗茎は、縄文時代には既に食用とされていました。
ヤマユリの鱗茎は、大型で苦味がなく美味なことから、戦国時代には城内に非常食として植えられ、戦後の食糧難時代にも貴重な栄養源となりました。
百合の名は、鱗茎の鱗片が重なり合う様を表したものとされています。ウィーン万国博覧会(明治6年)で日本の他のユリと共に欧州に紹介され、英国でもqueen of lily(ユリの女王)の名を獲得しました。以来、ユリ球根は大正時代まで主要な輸出品のひとつでした。
 漢方では鱗片をほぐしてから熱湯を注いだ後に日干ししたものを「百合」(びゃくごう)と呼び栄養補給のほか、去疾、利尿に用います。民間では、咳き止め、解熱、消炎などに用いられます。
漢方では鱗片をほぐしてから熱湯を注いだ後に日干ししたものを「百合」(びゃくごう)と呼び栄養補給のほか、去疾、利尿に用います。民間では、咳き止め、解熱、消炎などに用いられます。