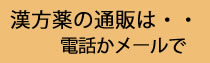■ 漢方治療の現場から・・・・喘息
気管支喘息の二大症状とメカニズム
気管支喘息の二大症状は、呼吸困難と喘鳴です。気道が広範囲に狭窄することによって起こります。
何らかの原因で気管支がれん縮すると、気管支の内腔が細くなります。また、粘液の分泌が亢進すると、たんが生じてからみやすくなります。炎症によって気管支の内壁がむくむので、気管支に痰がよけいにつまりやすくなり、呼吸困難になります。空気を吸うよりも吐くほうが困難になり、細くなった気道と呼気が摩擦したり、痰を突き破るため、ヒューヒュー・ゼーゼーという音が起こります。発作は通常の可逆性であり、発作が起きていないときは無症状です。
肺の働きと呼吸の仕組み 中医学の立場から
気管支喘息とは
気管支喘息は呼吸困難を主な症状とする疾病で、中医学では哮喘(こうぜん)と呼んでいます。 哮(こう)は、水液代謝の異常によって生まれた病因(「飲」や「痰」)が「肺」の中にひそんでいるところに、外因が浸入したり(かぜなど)、飲食の不節制や感情のうっ積や変動、過労などの内因が加わるために発症する、急性の激しい呼吸困難をさし、ヒューヒューという音をともなうのが特徴です。これに対して喘[ぜんは、急性あるいは慢性の疾病の経過中に起こる呼吸困難をさします。
さまざまことが気管支喘息の引き金になる
体に飲や痰などの病根がひそんでいるときに、気候の異常な変化の影響を受けてかぜをひいたり、生ものや冷たいものの食べすぎや飲みすぎ、辛いものや油っこいものの食べすぎで胃に負担をかけたり、感情の急変や過労などによって内臓の機能が乱れると、体の抗病力が低下して、ひそんでいた病根が動きだします。病根は「水の通り道」を通って肺にあふれ、肺のはたらきを妨げます(肺失宣降
[はいしつせんこう])。こうして気管支喘息の発作が起こります。
最も引き金になりやすいのは熱(風熱感冒)と寒さ(風寒感冒)です。熱は痰を刺激し、寒さは飲を刺激して、正常な体のはたらきを障害しやすい傾向があります。次いで引き金になりやすいのは感情の急激な変化です。
気管支喘息の分類と治療
現場での治療は急性期ではなく体質改善を目的とした治療が中心になってきます。発作を繰り返したり、肺や脾胃、腎などのはたらき失われて、呼吸困難やせき、たんのほか、発汗しやすい、元気がない、胃腸が弱い、腰が重い、浮腫といった症状をいつもともないながらかぜをひいたり、季節の変わり目に慢性の激しい呼吸困難を引き起こすのは、虚の喘息です。
気管支喘息の発作がおさまったら、病因となった飲や痰を除くとともに、衰えたり失われた内臓の正常なはたらき(気・血・陰・陽)を補います。特に肺と腎、あるいは肺と脾胃の治療が大切です。
漢方薬アドバイス
呼吸困難で息を吐きにくいときは肺に、息を吸いにくいときは腎に問題があると考えます。腎を補うには「
六味丸」や「
八味丸」を使います。
また、肺と脾胃のはたらきが失われているときは、「
六君子湯」や「
黄耆建中湯[おうぎけんちゅうとう]」、「
補中益気湯[ほちゅうえっきとう]」や「
参苓白朮散[じんりょうびゃくじゅつさん]」が基本薬となります。
生活アドバイス
●規則正しい食生活や運動
●冷たいたいものを食べ過ぎない
●ストレスを避け、リラックス
●部屋を清潔に